こんにちは。hiroです。
「日本の家庭の家事負担をゼロにする」ことを目標に家事負担を減らす方法を研究しています。
片付けたいけど、やる気が起きない・・・と悩んでませんか?
そんな時はモチベーションサイエンスを参考に、自分自身を動かす方法を学びましょう。
モチベーションサイエンスとは、その名の通り人間のモチベーションを研究する心理学の分野です。
比較的新しい分野で、多くの場合、従業員のモチベーションを上げる、生徒の学習意欲を上げるなど、他人の行動をどう変えるかという目的で研究が行われています。しかし、このモチベーションサイエンスの知見は自分自身を動かすことにも活用できます。
今回は、モチベーション心理学の研究をリードするアイエレット・フィッシュバックさんの著書「科学的に証明された自分を動かす方法」を参考に片付けのモチベーションを上げる方法を考えていきましょう。
- モチベーションサイエンス学会の元会長
- シカゴ大学ブース・スクール・オブ・ビジネスの心理学教授
片付けのモチベーションを上げる方法を学べば、キレイな部屋への道のりを一歩づつ歩んで行けるはずです。一緒に頑張りましょう!
モチベーション科学に学ぶ、片付けのやる気スイッチの入れ方
モチベーションはどうすれば出せるのだろう?一言で言うなら、答えは「環境を変えること」だ。
アイエレット・フィッシュバック. 科学的に証明された 自分を動かす方法なぜか目標を達成できてしまう、とてつもなく強力なモチベーションサイエンス (p. 5). Kindle Edition.
モチベーションサイエンスでは、環境を調整すれば人の行動は変わることを基本原理としています。
言い換えると、自分自身を無理に動かさなくても、環境を変えれば、モチベーションが上がり、行動に移せると言うことです。
では、具体的にどのような方法でモチベーションを上げるのでしょうか?今回は、以下の8つのポイントに分けて解説していきます。
- 適切な目標を立てる
- “ご褒美”を使いこなす
- 進捗を測る
- 失敗に備える
- 片付け以外の目標との両立法を知る
- 誘惑との戦い方を知る
- 辛抱強く努力し続ける
- みんなの力を借りる
上から順番に実行する必要はありません。自分が気にいったものから取り入れていきましょう。1つ取り入れるごとにモチベーションが少しづつ高まっていくはずです。
目標の立て方でやる気スイッチを入れる

適切な目標を立てましょう。
目標の立て方を変えるだけで、モチベーションを上げられます。
モチベーションが上がる目標を立てるには、以下のポイントを押さえましょう。
ワクワクすること:想像するだけでワクワクして何かをしたくなる目標がベストです。ポイントは、「こうなりたい!」という自分の感情を大切にすることと、目標が手の届く範囲だと思えることです。この2点を押さえれば、きっとワクワクする目標が立てられます。
次に何をするかがわかること:いくらワクワクする目標と言っても、壮大すぎるものはよくありません。基準は、「次に何すれば良いのかがわかること」です。壮大すぎて何すれば良いかわからない目標では、実際の行動につながりにくくなります。次の具体的な行動がイメージできる目標が良いでしょう。
単なるタスクとは思えないこと:目標とタスクは分けて考えましょう。具体的な行動がわかるとは言っても細かすぎるタスクを目標にしてしまっては、ワクワク感がなくモチベーションの低下につながります。
数値が入っていること:これはできればで構いません。難しいけど不可能ではなく、行動に結びつくような数値を目標に入れましょう。1日30分片付ける、週に1つ何かを捨てる、〇〇日までに片付ける、などが良い例です。思いつかなければあいまいにしておきましょう。また、測定に手間がかからないことも重要です。
自分で決めること:当然ですが、自分で決めることが大切です。他人から無理に押し付けられた目標ではモチベーションは上がりません。
例えば、以下のような目標は上記のポイントを押さえていると言えます。
- 子供が生まれるまでに、子供がのびのびと遊べる家にする。
- 今年のクリスマスは友人を呼んでホームパーティーをする。
- ミニマリストになるために、1日1つ物を減らす。
ただし、目標に正解はありません。上記はあくまでも例です。正解を目指すより自分で目標を考えることが大切です。なぜ自分は「片付けたい」と思ったのでしょうか?まずは自分の気持ちをよく聞いて目標を立ててみましょう。
やる気を継続させる”ご褒美”の使い方

モチベーションの維持にはインセンティブが欠かせません。
人間は長期的な目標の追求が苦手な生き物です。将来のメリットは今手に入るメリットに比べ価値が低く感じます。今頑張っても、「今」ではなく「将来」のメリットになるならモチベーションは上がらないのです。
そこで使われるのがインセンティブです。長期的なメリットの他に、すぐに手に入る小さなメリットを設定することで活動に対するモチベーションを上げられます。
片付けも長期的な目標です。インセンティブを上手く活用する必要があります。
では、インセンティブを上手く活用するには、どうすれば良いのでしょうか?
内発的モチベーションを高めよう
まずは片付けに対する内発的モチベーションを高めましょう。
内発的モチベーションとは、「活動に強く結びついた報酬のためにその活動をおこなうモチベーション」です。簡単に言えば、楽しいことは苦にならないのです。
例えば、「運動すると気持ち良いから運動する」というのは運動に対して内発的モチベーションが高い状態です。反対に「健康のために運動する」というのは内発的モチベーションは高くない状態です。
内発的モチベーションが高い人は、ない人と比べ目標に対して熱心に取り組む傾向があることがわかっています。*1
これはぜひ片付けにも活かしたいですよね。では具体的に内発的モチベーションを高めるにはどうしたら良いでしょうか?
*1 アイエレット・フィッシュバック. 科学的に証明された 自分を動かす方法―なぜか目標を達成できてしまう、とてつもなく強力なモチベーションサイエンス (Japanese Edition) (p. 81). 東洋経済新報社. Kindle Edition.
内発的モチベーションを高める3つの方法
内発的モチベーションを高めるポイントは、活動した瞬間に報酬が得られる(=楽しく感じる)工夫をすることです。
ここでは、具体的な方法を3つ紹介します。
既知の楽しさに集中する:片付けた時に即座に得られる報酬はないでしょうか?例えば、「片付ければ気分がスッキリする」、「片付けた場所が綺麗になる」「目標に向けて頑張っている自分に自己肯定感を感じる」という当たり前だけど見過ごしがちなメリットがあるはずです。こうしたすぐに得られる報酬を意識するだけで内発的モチベーションが高まります。
面白い手段を取る:目標に向けた活動は1つだけとは限りません。選択肢が複数あるなら自分が楽しめるものを選んでみましょう。例えば、1人で片付けるよりも誰かと片付ける方が楽しいなら家族と時間を合わせて片付けてみましょう。またゴミ箱に的を設置すればゴミを捨てるのも少し楽しくなります。
make it fun戦略:活動と即座に得られる報酬を意図的に結びつける方法です。特に目標に向けて努力している最中に限定して誘惑を許すとより効果的です。例えば、「片付け中だけ音楽を聞いて良い」などとというルールを作るのが良いでしょう。活動中に即座に気分が良くなる工夫がないか考えてみましょう。
ただし、内発的モチベーションだけではどうしても行動に移せない場合もあることも現実だと知っておきましょう。内発的モチベーションは強力ですが、それを得るにはハードルが少し高いのです。
では、内発的モチベーションだけでは十分にモチベーションが高まらない場合は、どうすれば良いのでしょうか?
外発的モチベーションを活用するときの注意点
内発的モチベーションのみでは行動に移せない場合、外発的モチベーションの活用を検討しましょう。
例えば、「片付けを頑張った日の夕飯は外食で美味しい物を食べる」などです。
外発的モチベーションとは内発的モチベーションと異なり、活動に強く結びついていないモチベーションです。簡単にいうと「楽しくないけど得だからやる」といったものです。
いまいち気乗りしない時や、後一歩で行動できるような気持ちの時に外発的インセンティブを足すのは良い方法です。しかし、外発的モチベーションは取り入れ方に注意しないと、反対にモチベーションを下げる結果になることもあります。
ここでは、外発的モチベーション活用時の注意点を学びましょう。
外発的インセンティブでモチベーションが下がる時を知ろう
効果的ではない外発的インセンティブ設定のデメリットを見ていきましょう。
本来の目標へのコミットを弱める:特に目標を立てた当初は注意すべきです。目標を立てた当初は、自分でその活動をなぜ行うかを探っている時期です。自分でも「なぜその活動をするのか」完全に整理できてない時期に外発的報酬を設定すると、目標へのコミットメントが弱くなってしまいます。目標へのコミットメントの強さはモチベーション維持において最も大切です。目標を立てた当初に外発的報酬を設定するのは注意しましょう。
過剰正当化効果:過剰正当化効果とは、内発的モチベーションが高い活動に外発的インセンティブを与えると、内発的モチベーションが減退してしまう現象です。もともと楽しいと感じる活動へのインセンティブは増やすべきではないのです。
希薄化の法則:インセンティブを増やすことは、その活動を行う理由を増やすことになります。人は活動を行う理由が多くなると、モチベーションが下がる傾向があります。「ゴミ捨て」の作業を例にします。片付けにもなって、部屋が清潔になって、ちょっとした運動にもなって、外の空気を吸いに行くことで気分転換にもなって、環境問題にも貢献できる、さらに捨て終わったらチョコレートも食べられる!・・・とたくさんの目的を考えると、なんとなく面倒になってきてゴミも捨てずにチョコ一個食べて終わりにしてしまうのが人間です。
ズルできるかもしれない:インセンティブがズルしても獲得できる場合、本来の目的に貢献しない活動が増える可能性があります。例えば、「ゴミ袋1つ分断捨離したら、1000円お小遣い増額!」というルールを設定した場合、何か安く大きなものを買ってきて断捨離したことにする、他の家族の物をこっそり捨てる、ゴミをこっそり混ぜるなど、さまざまな抜け穴が見つかります。こうしたインセンティブは目標達成に貢献しないため失敗と言えるでしょう。
外発的報酬が消えるとモチベーションが下がる:報酬が増えると、本来の目的と活動との結びつきを弱め、報酬と活動を結びつけるようになります。その状態で報酬が消えた場合、当然活動に対するモチベーションも大きく下がります。
大切ではないインセンティブを設定してもモチベーションが下がる:特に家族に対するインセンティブを設計する際に気をつけましょう。大切だと思わないインセンティブを設計した場合、インセンティブへの気持ちが弱まると同時に、活動へのモチベーションも下がります。
いまいち気乗りしない時や、後一歩で行動できるような気持ちの時に外発的インセンティブを足すのは良い方法です。しかし、外発的モチベーションは取り入れ方に注意しないと、反対にモチベーションを下げる結果になるため慎重に検討しましょう。
進捗を測ればやる気が継続する

何か長期的な目標に向けて頑張っている時、自分がどれくらい進んでいるのかを認識することはモチベーションを保つ上で重要です。
進捗を測ることがモチベーションに維持に役立つ理由は、状況により様々ある*2のですが、ほとんどの場合において、進捗の測定はモチベーションを上げる効果があります。(原理について詳細が知りたい方は書籍を参照してください。)
片付けにおいては、以下のポイントを押さえて進捗を図りましょう。
- まずは完了した実績に注目する
- 軌道に乗ったら小範囲の法則を活かす
- 期間を細かく区切って中だるみを防止する
- ボーナスポイントを活用する
- 測定に手間をかけない
*2: アイエレット・フィッシュバック. 科学的に証明された 自分を動かす方法―なぜか目標を達成できてしまう、とてつもなく強力なモチベーションサイエンス (Japanese Edition) (p. 110). 東洋経済新報社. Kindle Edition.
片付け初心者はまず「完了した実績」に注目しよう
進捗を確認した後、完了したものと、未完了のものどちらに注目すべきでしょうか?
実は進捗確認のモチベーションへの影響は、完了したものに注目するか、未完了に注目するかで効果が変わります。さらに複雑なのは、状況によって効果が逆になるという点です。
以下の表に状況ごとにどちらに注目するとモチベーションが上がるのか、まとめました。
| 未完了に注目すべき | 完了に注目すべき | |
| 明確なゴール | あり | なし |
| 目標へのコミット度合い | 強い | 弱い |
| 自分の熟練度 | ベテラン | 初心者 |
ご自身の状況に合わせてどちらに注目すべきか考えてみましょう。例えば、みなさんが片付け初心者であるなら基本的には進捗を振り返る方がモチベーション良い影響を与えます。
軌道に乗ったら小範囲の法則を活用しよう
完了に注目すれば、スタートダッシュは上手く切ることができます。ただし、これだけで永遠にモチベーションがつづくとは限りません。
理由は目標勾配効果です。
完了したものが少ない場合には、1回の活動で得られる効果は相対的に大きくなります。一方、何度も活動を行なった後は1回の活動で得られる効果は相対的に小さくなります。つまり、「1024→1025」よりも「0→1」の方が大きく感じるのです。
そんな時は、ゴールを設定し未完了のタスクに注目しましょう。ゴールまでもう少しだと思えば、頑張る力も湧いてきます。つまり、「残り99%→残り98%」より「残り1%→完了!」の時の方が頑張れるということです。
では、いつ未完了タスクに注目し始めれば良いのでしょうか?これに小範囲の法則が役立ちます。完了と未完了の小さい方に注目するというテクニックです。とりあえず小さい方に注目してくれば、目標勾配効果がより大きく働く方に注目できるのです。
期間を細かく区切って中だるみ防止
できるだけ期間を細かく区切って測定しましょう。
スタート付近とゴール付近は、みんなモチベーションが上がるものです。(学生時代の長距離走を思い出してください。)逆に考えると、中間付近はモチベーションが下がりやすいのです。
それならば、測定するスタートとゴールを細かく区切って、モチベーション維持が難しい中間をできるだけ短くしてしまいましょう。
長距離走とは異なり、片付けに対するスタートとゴールは自分が自由に決められます。毎朝「今日が始まりの日だ」と口にしてみるだけでも効果はあります。
ボーナスポイントを活用する
ボーナスポイントとして、幻の実績を作りましょう。
近所のお店のスタンプカードをつくる時に、最初からスタンプが押されていた経験はありませんか?これは人の心理を上手く活用しています。
10枠のスタンプカードと、あらかじめ2つスタンプが押してある12枠のカードは論理的には同じです。しかし、すでに2つスタンプが押してあるカードをより埋めたくなってしまうのが人間なのです。
この心理を片付けにも活用しましょう。例えば、進捗を記録するカレンダーに2日間ほどをボーナスポイントとしてチェックマークをつけるだけで、片付けを続けるモチベーションが高まるはずです。
手間がかからない方法にしよう
進捗は手間がかからない方法で測定しましょう。
進捗を測る手間が多いと、それ自体が面倒になりモチベーションを下げる原因になります。
例えば、「片付けたものの数を測定する」のは避けましょう。片付けたものを数えることに労力が取られてしまいます。「片付けた時間を測定する」、「片付けた引き出の数を確認する」といった、多少粗くても数秒で行える程度の測定方法を考えてみましょう。
正確に進捗を測ることは目的ではありません。進捗を測りモチベーションが上がることが目的であることを意識して測定方法を考えてみましょう。
具体的な進捗の測り方の例
これまでのポイントを踏まえた、具体的な進捗の測り方の例を紹介します。
カレンダーを使う
10分の片付けなどのルールを作り、守れた日にチェックをつける方法です。これまでのポイントを抑えるために以下の工夫をしましょう。
- 期間を1週間ごとに区切る(小範囲の法則、中だるみの防止)
- 前の1週間に完了マークをつける(ボーナスポイントの活用)
- 小範囲の法則を意識する。
- 壁にペンと共に貼っておく。(手間をかけない)
カレンダーとペンを買ってくれば、すぐにでも始めることができます。迷ったらこの方法でまずはスタートしましょう。
場所別に進捗を測る
片付けたい場所の写真を撮り、印刷しましょう。そこから片付けた場所を塗りつぶす方法です。
- 場所を上、中、下など小さく区切る(小範囲の法則、中だるみの防止)
- 空いているスペースなどにそもそも片付けなくて良い場所を塗りつぶす(ボーナスポイントの活用)
- 小範囲の法則を意識する。
- 壁にペンと共に貼っておく。(手間をかけない)
写真を印刷すれば、すぐに始められます。プリンターをお持ちではない方はコンビニのネットプリントを使うと便利です。
>>FUJIFILM.セブン-イレブンのマルチコピー機があなたのプリンターに
失敗に備える
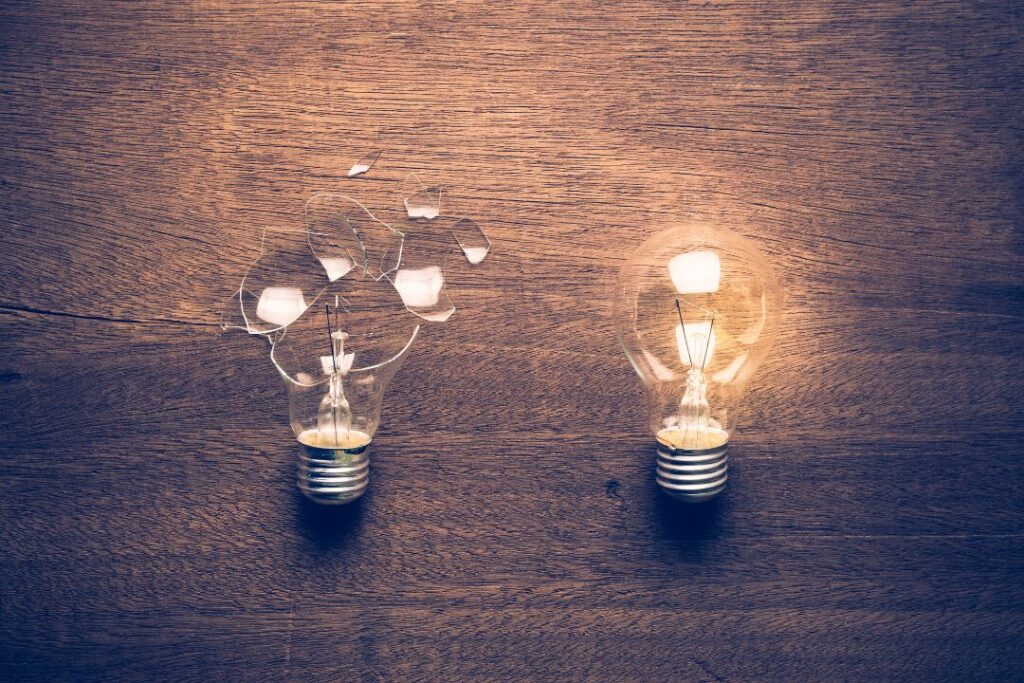
何かに挑戦した時に失敗はつきものです。片付けも例外ではなく、これから以下のような失敗をたくさん経験するでしょう。(全て私の経験談です。)
- 1日頑張ったのに、なんか綺麗になってない。
- 一生懸命整頓したのに、家族から「どこに何があるかわからなくなった」とクレームを受けた。
- 浮かせる収納を作ったら、すぐに落ちた。
- 家族の協力を得ようとしたが、なかなか協力してくれない。
こうした失敗を経験したときには、「自分にはムリなのではないか」と感じ、投げ出してしまいたくなるものです。しかし、こんな時に心を折られずに地道な努力を続られるかどうかが片付けに成功するかどうかの分かれ道です。
近い将来必ず訪れる「失敗」に備えてモチベーションを保つテクニックを学びましょう。
失敗してもモチベーションを下げないテクニック
失敗してもモチベーションを下げないテクニックは以下の通りです。
自分には無理なのか?とは問わない:この問いが思い浮かぶと、自分にこれは失敗であると言い聞かせてしまうことになります。とは言え無理に「成功だ!」と思い込むのも難しいものです。「自分には無理なのか?」と思ってしまった時は、以下で紹介する他の問いに切り替えてみましょう。
この経験から何が学べるか:その経験から何が学べるかを意識しましょう。何が学べるかに集中することで失敗したという意識が薄れ、前進している感覚に変えられます。どうしても気持ちを切り替えられない時は、私はつねに学んでいる、向上していると実際に声に出してみるのも有効です。
距離をおく:この失敗が自分ではなく、他の人に起きたことだと想像してみましょう。自分ではなく他の誰かに起きたことだと思えば、自尊心が傷つかずに冷静で客観的な目線で学べます。
他人にアドバイスする:同様の失敗をした他人がいると仮定し、その人にアドバイスしてみましょう。アドバイスするには、自分が何を学んだかを認識し、具体的な行動計画を立てる必要があります。これにより効率的に学べます。また、アドバイスすること自体で自信が回復する効果もあります。
進捗を確認する:一旦目標に対する進捗を確認しましょう。ポイントは自分の向き不向きや意志の強さを問わず客観的な進捗を確認することです。失敗した時点で、少なくとも行動しているということは、多少なりとも前進している証です。
目標に近づいたことを確認する:中間目標を達成できなかった時に有効です。ほとんどの場合、中間目標の達成自体は重要ではありません。重要なのは中間目標の達成に向けて行なった行動です。また、ギリギリ達成できなかった時ほど目標を投げ出したくなる、心理的な癖が人間にはあることも認識しておきましょう。
片付け以外の目標との両立法

人生には、片付け以外にもたくさんの目標があります。
子育て、運動、仕事、勉強などなど、日々たくさんのことをこなしている人にとって新しく片付けという目標をねじ込む隙間はないかもしれません。
それでも部屋を綺麗にしたい時、またはしなければならない事情があるときどうすれば良いでしょうか?
以下の手順に従って進めていけば、上手く他の目標とのバランスを取ることができます。
- 多目的型の活動を探す
- 目標に貢献する活動が1つしかないものを特定する
- 目標の優先順位を認識し、あとは直感を信じる
順番に解説していきます。
多目的型の活動を探そう
多目的型の活動を探しましょう。
多目的型の手段とは、複数の目標に貢献する活動のことです。例えば、自分に必要な服をあらかじめ洗い出しておく作業は、片付け、節約、おしゃれ、時短に貢献します。
この時、多目的型の手段は目標への貢献が弱い気がしてしまう心理的なクセに注意しましょう。人は1つの活動が1つの目標に結びついている時や、むしろ他の目標を損なう方がより高い効果があると思い込みがちです。(苦い薬はよく効きそうなイメージはありませんか?)
しかし、これは幻想です。多目的型の手段はほとんどの場合、最良の選択肢です。なんとなく効果を弱く感じてしまう心理を乗り越え、意識的に多目的型の手段を探しましょう。
目標に貢献する活動が1つしかないものを特定する
目標に貢献する活動が1つしかないものを優先しましょう。
目標に貢献する活動が1つしかないならば、それに時間を割かない限りその目標は達成されません。
例えば、収納を増やす、ラベリングするなど片付けにしか貢献しない活動がそれに当たります。
目標に対する手段が1つしかない場合は、それを意識的に優先しましょう。
目標の優先順位を認識し、あとは直感を信じる
どうしても時間が足りない場合、目標の優先順位を調整する必要があります。
そんな時には、
- 本当に最も大切な目標が何かを考える
- 自分の感覚を信じて取るべき行動を選ぶ
の2ステップを踏んでみましょう。
人は、できるだけ多くの目標にプラスの成果をもたらす行動を選ぶ傾向があります。これを「成果最大化の法則」と呼びます。
例えば、コンビニのチョコを買うかどうかは、健康と節約にマイナスの影響を与えますが、ストレスの減少やちょっとした疲労回復には貢献します。こんな時に人は、健康・節約・ストレス・疲れといったたくさんの目標をリアルアイムに処理して、その時最善だと考える選択をしているのです。
これを活かして、自分の目標を意識的に再認識した後は、自分の直感を信じてみましょう。成果最大化の法則により、そこまで大きく間違った選択はしないはずです。
誘惑との戦い方を知る

ここでは、誘惑との戦い方を学びます。
片付けが続かない原因の一つが目の前の誘惑に負けることです。
例えば、「部屋を片付けなきゃいけない」と頭ではわかっているのに、スマホを見てしまい、気づいたら1時間経っていたという経験はありませんか?
こんな時に、スマホという目の前の誘惑に負けず、きちんと片付けに取り組むためのテクニックを知っておきましょう。
まずは誘惑とは何かを考えます。
誘惑とは?
誘惑とは、「すべきこと」と「したいこと」が明確に分かれていて、「したいこと」が明らかに目標達成に役立たない、または阻害するもののことを指します。
上記の例でも、スマホは片づけには一切役に立たないため、誘惑と言えます。
他にも、雑誌を見る、寝る、ゴロゴロする、テレビやSNSを見る、お菓子を食べるなど、今必要はないけれど、どうしてもやりたくなるものが誘惑です。
これから紹介するのは、「すべきではない」が「やりたい」誘惑をできるだけ遠ざけるテクニックです。早速見ていきましょう。
まずは誘惑を察知しよう
誘惑は、まず察知することが大切です。
誘惑を誘惑であると気づくのは意外と難しいものです。
例えば、ハサミなどのちょっとしたものを机に置きっぱなしにしたり、スマホに何か通知が来た時に反射的に確認し、そのままSNSを見続けてしまったことがある方もいるはずです。
後から考えれば、誘惑に負けたと思うかもしれませんが、その場では誘惑であることに気づきすらしていません。
当然ですが、誘惑だと気づいていないものとは戦えません。まずは誘惑に気づくテクニックを学びましょう。
誘惑を察知する方法1:広い判断フレーム法
広い判断フレーム法とは、その行動を積み重ねた時にどうなるかを考えるテクニックです。
誘惑に負けた時の影響が小さい時、人は誘惑に気づきにくくなる性質があります。
それならば、誘惑に負けた時の影響を大きく感じるように工夫することが対策になります。具体的には「積み重ね」で行動を捉えるのです。
例えば、「片付けをするつもりだったけど、少しだけSNSを確認しよう」と思った時に、これが積み重なり1年後も結局散らかった部屋のままになった未来を想像してみましょう。
こう思うとSNSは我慢しなければならない気がしてきませんか?これが、広い判断フレームテクニックです。
誘惑を察知する方法2: 自分は片付けられる人間だと言い聞かせる
自分は片付けられる人間であると自分自身に言い聞かせましょう。今現在片付けが上手でなくても構いません。自分で思い込むことが大切です。
人は、自分のアイデンティティと異なる行動を取ると違和感を感じる性質があります。
自分のアイデンティティを「片付けられる人間」だと無理にでも思い込むことができれば、ちょっとした置きっぱなしも気になるようになります。
具体的には、以下の手段が有効です。
朝一で何かを片付けるようにする。朝一の行動は自分自身に自分のアイデンティティを刷り込む良いタイミングです。このタイミングで片付けをすれば、自然と「自分は片付けられる人間である」と思えるようになります。逆に、朝一で何か散らかすような行為をするとそれが自分自身への「自分は片付けられない」というメッセージになるので、気をつけましょう。
SNSに片付いた綺麗な部屋(の一部分でも)を無理やりにでもアップする。ちょっと強引な手段ですが、効果は抜群です。周囲の方に「自分は片付けられる人間である」と宣言すると同時に、自分自身へも強いメッセージを送ることに繋がります。
ここまでが誘惑を察知する方法です。誘惑だと認識できたら、いよいよ誘惑と戦うテクニックを学びましょう。
どんな誘惑がいつ来るか予測する
誘惑がいつ来るか、どのくらい強いものかをできるだけ正確に予想することが大切です。
いつ、どのくらい強い誘惑が来るかわかれば、それに対する対策を打てます。
例えば、家に帰った後服を脱ぎっぱなしにしてテレビを見るクセがあるなら、洗濯カゴをあえてテレビの前の邪魔な場所に置いておく、パートナーに脱ぎっぱなしが見つかったら500円を払うルールを作るなど、様々な対策が取れます。ただ単に「帰ったらまず服を洗濯カゴに入れるぞ!」とドアを開ける前に覚悟を決めるだけでも効果があります。
反対に、予期していない誘惑に逆らうことは難しいものです。まずは予測することから始めましょう。
誘惑に流されにくい状況にしておく
誘惑に流されにくい状況にしておきましょう。
このようなテクニックをプリコミットメントと呼びます。事前に、やると決めたこと以外の選択肢をなくしておく方法です。
例えば、片付けると決めた日に合わせて買取業社やトランクルームの予約をその場で完了させましょう。業社さんが来る予定が決まっていれば、片付けをきちんとやり遂げようという気になります。
片付けが進まない2大原因は「不要だけど高価だったから捨てられない」、「思い出があるから捨てられない」です。
高価だったものは買取へ、思い出のものは宅配型トランクルームへ預けるだけで、片付けは劇的に進みます。
>>断捨離をグッと前に進める買取業者の選び方とオススメのお店を紹介
>>収納もサブスクの時代!宅配型トランクルームサービスとは?
誘惑に流される選択肢をあらかじめなくしておけば、誘惑に勝ちやすくなります。
誘惑に対するペナルティを設定する。
誘惑に屈したら自分にペナルティ、屈しなかったらインセンティブが出るようなルールを作りましょう。
単純ですが、前述の誘惑に流される選択肢を無くす方法がない時に、有効なテクニックです。
例えば、朝一で5分間片付けなかったらお小遣い500円減額し、片付けられたら500円増額といったルールを設定しましょう。このルールがあれば朝起きて眠い状態でも、お小遣い減額を避けるため片付ける気になるはずです。
なお、ペナルティかインセンティブかどちらかしか設定できない場合は、ペナルティの方が有効です。人は何かを得ることよりも、何かを失うことの方に過敏に反応します。*3そのため「お小遣いを失う」ことを避けるために積極的に行動を起こそうとするはずです。
*3: プロスペクト理論. (2024). Retrieved 12 October 2024, from https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E7%90%86%E8%AB%96
誘惑から距離を取る
誘惑から距離をとりましょう。
これも単純ですが、距離が遠ければ遠いほど誘惑に抗いやすくなります。物理的な距離でも構いませんし、時間的な距離でも構いません。
例えば以下のような手段があります。
アルバムの片付けは家族やパートナーに任せる。片付け中に、思い出のアルバムを見てしまって進まないなら、アルバムの処理はパートナーに任せましょう。
SNSのアプリを削除する。ついついSNSに流されてしまう方に有効です。SNSを見るのにアプリがなければ、ブラウザから見るか再度ダウンロードする必要があります。この1手間がSNSと距離をとることにつながります。
スマホを遠い部屋に置く。どうしてもスマホを見てしまって片付けが進まないなら、この手段です。スマホが目の前にないなら、スマホの誘惑も我慢しやすくなります。
物理的、時間的に誘惑からできる限り距離をとりましょう。
誘惑の魅力的ではない側面をたくさん思い出す
誘惑がそれほど魅力的ではない理由を意識しましょう。
例えば、ソファに横になってダラダラしたい誘惑に駆られた時は、姿勢が悪くなる、時間が取られる、貴重な時間を浪費する、そのまま寝たら風邪引くかも・・・などなど、多少強引でも良いので誘惑の悪い側面をできるだけ多く思い出しましょう。
同時に、片付けをすればカフェのような空間で自宅でコーヒーが飲めるなど、目標が魅力的であることを再認識するとより効果的です。
誘惑が魅力的ではない理由が多いほど、誘惑の価値が目減りしていき、誘惑に抗いやすくなります。
誘惑を冷却の言葉で表現する
誘惑を「冷却の言葉」で表現してみましょう。
「冷却の言葉」とは認知的・情緒的にニュートラルな表現のことです。
例えば、休日に片付けなんてせずに買い物に出かけたい!と思った時を想像してみましょう。買い物を「楽しくてワクワクするお出かけ」などと表現せずに単に「家とショッピングモールを往復する」とあえて口にだしてしてみましょう。
こうするだけで誘惑と心理的な距離を取ることにつながり、誘惑に負けない選択を取りやすくなります。
自分自身にアドバイスしてみる
今自分が誘惑と戦っているなら、似たような葛藤に直面している他人にどうアドバイスするか、想像しましょう。
人は自分ではない誰かの話なら冷静に判断できるものです。(自分のことを棚に上げて・・・とよく言いますよね。)
他にも以下のような問いかけを自問自答するのも効果的です。
- <自分の名前>は今何をすべきなの?(一人称の「私」ではなく三人称の「自分の名前」を使ってみるのがポイント)
- <自分が憧れる人の名前>だったらこの行動をするかな?
- 来年同じ状況になったら、自分はどういう行動を取るか?
その葛藤が別の人間、別の場所、別の時間で起きていると感じれば、自分自身の今現在の問題ではなくなり、冷静な判断ができるようになります。
習慣にする
ここまで、誘惑との戦い方を解説してきました。しかし、そもそも誘惑と戦うのは疲れるという問題があります。
そこで、とりたい行動を習慣にしてしまいましょう。習慣なれば、体力を消耗せず、自動的に理想的な行動を取れるようになります。
習慣にするには、「〇〇という状況になったら〜〜をする」という実行意図*4を作り、これを実行する方法がシンプルかつ効果的です。
例えば、「夜帰ったら、まず机の上の綺麗にする」といった実行意図(=ルール)を作って今日から実践しましょう。初めは強く意識する必要がありますが、慣れれば無意識に行動できるようになります。
習慣にしてしまえば、体力を消耗せず、また疲れた時にも自動的に理想的な行動が取れるようになります。
*4 Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. American Psychologist, 54(7), 493–503. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.493
辛抱強く努力し続ける工夫

片づけには、どのくらい時間がかかるのでしょうか?参考に、プロによる不用品撤去の事例をみてみましょう。
ドクターエコさんの事例集によると、家一軒片付けるのにおおよそ作業人数5名で5時間の時間がかかっています。*5(注意:事例によりかなり差があります。気になる方はリンク先を参照して下さい。)これは1人で片付けると仮定すると25時間の作業時間です。1日1時間片付けに時間が取れる場合には、大体1ヶ月かかる計算です。
さらに、この事例はプロによるものであること、また不用品を撤去するだけと片付けの一部分のみ作業であることも考慮すると、家丸ごと片付けるためには、少なくとも数ヶ月に渡る努力が必要があることがわかります。
片付けが苦手な方にとって、この道のりは遠く辛いものに感じる時もあるはずです。そんな時に心を折られずに地道な努力を続けるためにはどうしたら良いでしょうか?
ここでは、そんなテクニックをいくつか紹介します。
*5 ドクターエコ. 家をまるごと片付けるといくら?業者が一軒家の残置物撤去した費用相場を12軒から比較. (2024). Retrieved 12 October 2024, from https://dr-eco.jp/zantibutsu/kodate-12-price/
選択待機のテクニックを使う
片付けを諦めたくなったら、まず冷静に考える時間をとることにしましょう。
この時点で諦めないと決めなくてもOKです。諦めるか、続けるかを決める前に、まず5分でも良いので時間を取ることが大切です。
選択を保留にすることで、まず冷静になれます。冷静になることで、「家に人を呼べるようになる」などの片付けを頑張るメリットを再認識できるのです。
また、待機時間として自分の時間を使うとその分、目標とする片付いた部屋に対する愛着がわく効果も期待できます。
これらの効果により、まず時間を取るだけで「片付けを諦めない」という選択をしやすくなります。諦める前にまず時間を取りましょう。
事前決定のテクニックを使う
片付けの計画を事前に立てましょう。
人は、将来よりも目の前の利益を重視する傾向があります。一方、時間差の感覚は絶対的なものではなく、1年後と1年1ヶ月後の差は、今日と来月の差よりもずっと小さく感じられます。
この人間の心理を活用するのが「事前決定のテクニック」です。このテクニックでは、片付けをする日時と具体的なタスクをあらかじめ決めておきます。
計画を立てる際は、少し先の日程を選ぶことがポイントです。これにより、現在の気分に左右されない、客観的な判断ができます。
事前に計画を立てることで、片付けへの取り組みがより確実になるはずです。
とにかく忙しくする
諦めそうになったら、とにかく忙しくしましょう。
忙しすぎて、片付けを投げ出したくなっている事実を頭から追い出せれば成功です。(失恋した時に仕事に没頭して失恋について考えないようにするテクニックは有名ですよね。*6これと同じテクニックです。)
このとき、必ずしも片付けにこだわる必要はありません。料理や仕事、子育てなど、没頭できる別の活動でも構いません。忙しくすることが大切です。
目の前のタスクに集中せざるを得ない状況にすることで、自然と「片付けを諦めてしまおうか」という悩みが薄れていきます。
*6 経験者300人に聞いた「失恋した時」の過ごし方、やって良かった行動・NG行動TOP10. (2024). Retrieved 13 October 2024, from https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000222.000032757.html
未来の自分に手紙を書こう
未来の自分に手紙を書きましょう。
片付けは今の自分が頑張っても、得をするのは未来の自分です。
人は未来の自分は他人のように感じる傾向があります。未来の自分のことを他人のように感じるのであれば、今頑張るモチベーションが下がってしまうのも仕方ありません。
これを避けるには未来の自分との心理的な結びつきを強める(=未来の自分も自分であると感じる)のが有効です。
未来の自分に手紙を書くのは、未来の自分を身近に感じる有効なテクニックです。もっと手軽な手段では「未来はいつか現実になる」と自分に言い聞かせるのも良いでしょう。
家族と一緒に片付けを頑張る
家族と片付ける目標を共有しましょう。
何かを辞めたい!と思った時でも、人はその目標を誰かと一緒に頑張っているという事実のみで我慢強くなれるものです。
部活や仕事、受験などで辛い時も、仲間がいるから頑張れる!と思った経験がある方は多いのではないでしょうか?人は仲間と一緒なら、なんでも頑張れる動物なのです。
片付けという目標はぜひ一緒に住むご家族やパートナーと共有してください。次章では、家族と一緒に片付けるためのテクニックを学んでいきます。
みんなの力を借りよう

ここでは周囲の方の力を借りて、片付けのモチベーションを維持する方法を解説します。
人は社会的動物です。自分1人で頑張るよりも誰かと一緒の方が何倍も頑張れます。
特に家族全員で、「片付け」という目標を共有できた時の力は強力です。
周囲の方の力を借りて、片付けのモチベーションを保つテクニックを学びましょう。
誰かに「片付ける」と宣言しよう
誰かに「片付ける」と宣言しましょう。
人はただ誰かに見られているというだけで、1人の時よりも頑張る性質があります。人は誰しも、他人には最高の自分を見せたいものです。これを社会的促進と言います。
「片付ける」と宣言する以外にも、社会的促進を活かす方法はあります。
- SNSに片付けると宣言する
- 片付けを応援してくれそうな誰かの写真を置いておく
大切なことは誰かに見られている感覚です。誰かに見られている感覚があるだけで、モチベーションは高まります。
片付けを家族の目標にしよう
片付けを家族の目標にしましょう。
片付けという目標を共有すれば、頑張り続けるようにお互いで励まし合えます。
さらに、人間には集団で上手くチームワークをとる力が元々備わっています。「片付け」を家族の一つの目標にできた時には、うまく役割分担して、効率的に片付けを進められる可能性も秘めているのです。
ぜひ、片付けを家族の目標にしましょう。
ではどうすれば、片付けを家族の目標にできるのでしょうか?
片付けを家族の目標にするには??
片付けを家族の目標にする最も良い方法は、自分が「片付けをする」と宣言し、しっかり実行することです。
理由は以下の通りです。
同調:人は他人につられる性質があります。特に近い関係であるほど受ける影響は大きくなります。身近な人の目標は「あの人の目標」ではなく、「私たちの目標」であると感じるのです。
心理的重なり:人は身近な人が行ったことも、「私たちがしたこと」と捉えます。自分が片付けをすれば、家族も「私たちが片付けに向けて頑張った」と感じます。
目標に向けた行動実績が積み上がるとコミットメントが強まる:人は目標に向けた行動をとっただけで、その目標に価値があると思うものです。これに、先ほどの心理的重なりを合わせましょう。自分が片付けを頑張っていれば、家族は「これまで私たちが片付けをこれだけ頑張ったのだから、片付けはきっと大切な目標だ」と感じ始めるのです。
逆説的ではありますが、自分自身が片付けを頑張ること自体が、片付けを家族の目標にする第一歩なのです。
では、目標が共有できた後、さらにそれを促進するにはどうしたら良いでしょうか?
目標が共有できた後、家族に積極的に協力してもらう方法
家族に積極的に協力してもらうには、片付けに対する家族の貢献を見える化しましょう。
見える化すると「他の人の仕事量に対して自分はどうか?」、「自分がやった仕事はきちんとできただろうか?」と自然と考えるようになります。(上手くすれば、兄弟間で競争心が芽生えるかもしれません。)
方法としては、ホワイトボード等に以下の表を作成してみる程度でOKです。
| 名前 | 今日やったこと |
| ママ | 不要なTシャツを捨てた |
| パパ | 本を整理した |
| 〇〇くん | レゴを片付けた |
| 〇〇ちゃん | クレヨンを片付けた |
ただし、これは目標が共有できた後に行いましょう。家族が片付けを自分の目標だと捉えていない間は逆効果になってしまうことに注意しましょう。(目標の立て方の章でも触れた通り他人から押し付けられた目標ではモチベーションは上がりません)
今回参考にした書籍について
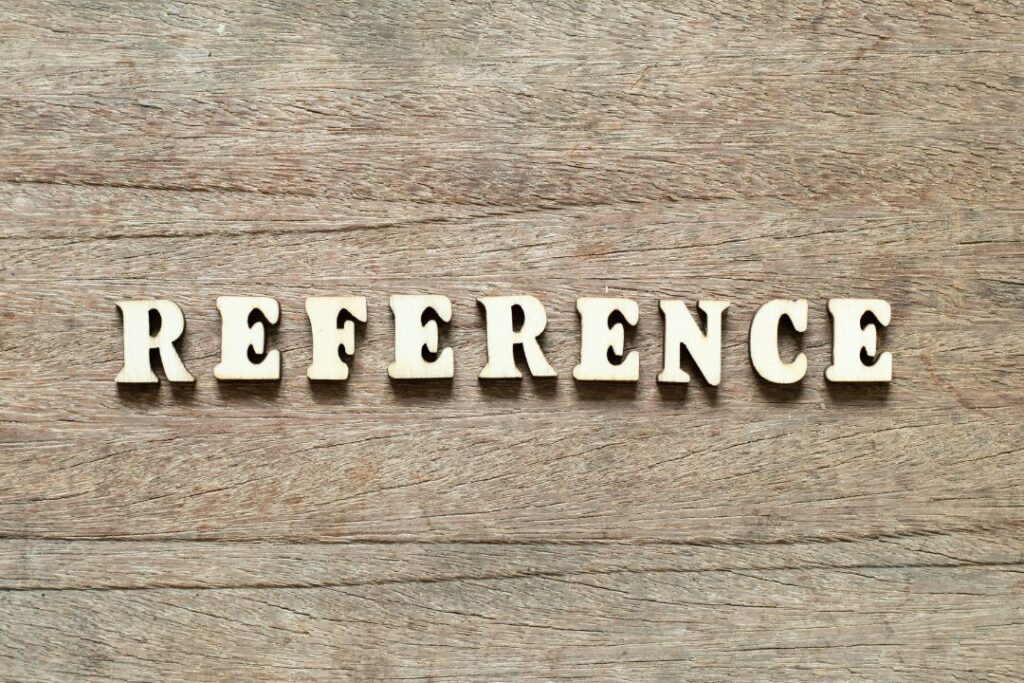
人生には、継続した努力が必要な場面はたくさんあります。
今回紹介した片付け以外にも、勉強、仕事、ダイエット、食事制限、筋トレ、部活、老後資金を貯める、といったことは全て継続した大きな努力が必要です。
元々モチベーションサイエンスとは、従業員のモチベーションを上げる、生徒の学習意欲を上げるなど、他人の行動をどう変えるかという目的で研究が行われることが多い心理学の1つの分野です。
この本は、モチベーションサイエンス学会の元会長がモチベーションサイエンスの知見を自分自身に活用する方法を、心理学に馴染みがない読者に向けて解説してくれている良書です。
自分を上手くコントロールして、人生をより良くしていきたい方は、ぜひ実際の書籍を読んでみることをおすすめします。
最後に今回の内容をまとめていきましょう!
まとめ:モチベーションが上がる工夫をいろんなところに仕掛けよう

今回は片付けのモチベーション維持の方法について解説しました。
片付けのモチベーション維持のポイントは以下の通りです。
- 適切な目標を立てる
- “ご褒美”を使いこなす
- 進捗を測る
- 失敗に備える
- 片付け以外の目標との両立法を知る
- 誘惑との戦い方を知る
- 辛抱強く努力し続ける
- みんなの力を借りる
これらポイントを押さえれば、片付けに対するモチベーションを上げて、維持できます。
今回の記事にはたくさんのテクニックを記載しています。簡単にできそうなものから、ぜひ実践してみてください。実践するごとに少しづつモチベーションが高まっていきます。
「早速片付けるぞ!」という人に読んで欲しい記事がこちら!
以上、hiroでした!
今回の記事についてみなさまはどう思いましたか?
ぜひ、みなさんのご意見・ご感想をコメントください!




